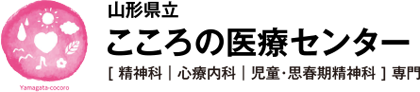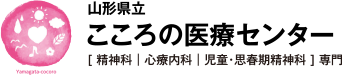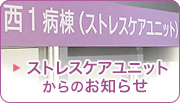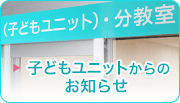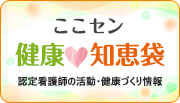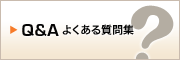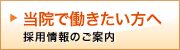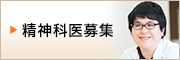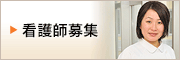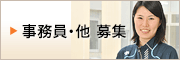当院では日本専門医機構認定【山形県立こころの医療センター専門研修プログラム】を実施しています。
このプログラムは当院が研修基幹病院となり、「山形大学医学部精神科」、「日本海総合病院精神科」、「東北会病院」、「三川病院」、「沖縄県立精和病院」、「東京医科大学病院」を研修連携病院として研修群を構成し、実施するものです。
令和7年4月1日現在、7名の専門研修医が当院の専門研修プログラムを実施しています。
専門研修プログラム冊子はこちら⇒(PDF形式 1016KB)
![]()
急性期から慢性期、乳幼児から老年期、任意入院から措置入院、更には医療観察法の入院までほぼ全ての精神科臨床領域を網羅的に研修できるプログラムです。このプログラムを研修することで、精神科医としての幅広い臨床経験が積める上、精神科医療を包括的に捉える視点が自然と身につきます。
![]()
- 外来患者、入院患者の診察を単独で行える。
- 精神科救急患者に対応できる。
- あらゆる精神疾患について診断、治療計画を立てることができる。
- 脳画像検査、脳波検査、心理検査の判定を行うことができる。
- チーム医療のリーダーとしての役割を果たすことができる。
- 他の医療機関、施設等関係機関との連携を図ることができる。
- 精神保健指定医、日本精神神経学会専門医の資格取得を目指す。
![]()
研修期間は原則3年間です。
1年目
- 指導医と一緒に統合失調症、気分障害、認知症、児童思春期等の患者を受け持ち、面接の仕方、診断と治療計画、力動的精神療法などの精神療法及び薬物療法の基本を学びます。
- 脳器質的疾患との鑑別診断も学習します。
- 精神科救急にも従事し、緊急入院の症例や措置入院患者の診察に立ち会ったり、入院患者を受け持ったりすることによって精神医療に必要な法律の知識についても学習します。
- 外来業務では指導医の診察に陪席することによって、面接の技法、患者との関係の構築の仕方、基本的な心理検査の評価などについて学習します。
- 院内のカンファレンスで発表し、討論を行います。
2年目
- 指導医の指導を受けつつ自立して診療を行い、面接の技術を高めると共に診断と治療計画の能力を充実させ、薬物療法の技法を向上させます。
- 気分障害、神経症圏患者の診断・治療を経験します。
- 他科と協働してリエゾン・コンサルテーション精神医学や緩和ケアを経験します。
- 認知症の画像診断、治療を学習します。
- 論文作成や学会発表のための基礎知識について学び、機会があれば地方会などで発表を行います。
3年目
- 指導医から自立して診療できるようにします。
- 精神療法を上級者の指導の下に実践します。
- 心理社会的療法、運動療法など精神科リハビリテーション、地域精神医療等を学びます。
- 児童思春期精神障害及びパーソナリティ障害、物質依存の診断・治療を経験します。
- 地域医療の現場に足を運び、他職種との関係を構築することについて学びます。
- 学術活動にも従事し、機会があれば地方会や研究会などで発表を行います。また、学会誌などへの投稿を行います。
【ローテーション例】 ※ローテーションは希望に応じます。
初年度:山形県立こころの医療センター
2年度:日本海総合病院
3年度:上半期:山形大学医学部附属病院または東京医科大学病院
下半期:山形県立こころの医療センター、日本海総合病院、東北会病院、山形大学医学部附属病院、三川病院、沖縄県立精和病院から選択
初年度は基幹病院である山形県立こころの医療センターにてスーパー救急病棟やストレスケア病棟での診療を中心に研修を行い、精神病圏、気分障害圏を始め、認知症、ストレス性疾患などの診療を経験していくなかでコアコンピテンシーの習得、倫理性の涵養など精神科医師としての素養を身につけることを特に重視します。
また、患者や家族に対する面接技法、疾患の概念と病態理解、診断基準の理解とそれに基づく診断、急性期対応、治療計画の策定、補助診断、薬物療法、精神療法及び心理社会療法、リハビリテーション、関連法規に関する基礎知識を習得します。
更に指導の下、術者として修正型電気けいれん療法を行います。症例検討会を定期的に行い、細やかな指導を行うほかに抄読会、勉強会などを行うことで学問的姿勢を深めます。
2年度は日本海総合病院にてリエゾン・コンサルテーション、緩和ケア、身体合併症を有する症例に対する診療を中心に研修します。
また、日本海総合病院においては日本老年精神医学会指導医が在籍し認知症疾患センターが設置されており、認知症の画像診断と治療についても研修を行います。救急当直を通じて、精神科のみならず全人的な医療を経験します。
3年度の上半期は山形大学医学部附属病院または東京医科大学病院で研修し、診療を行うだけでなく臨床精神薬理学、薬理遺伝学、老年期精神医学などの最先端の研究に触れ、学術活動にも従事します。
下半期は基本的に自由選択とし、専攻医自身が将来のサブスペシャリティーを見据えて研修先を選択することができます。基幹病院にて研修を行う場合は専攻医の希望に添ってスーパー救急病棟だけでなく医療観察法病棟やこども思春期病棟などの高い専門性を有する病棟での診療を中心に研修を行うことができます。東北会病院で研修する場合はアルコールを始めとする物質依存に対する診療について重点的に研修します。三川病院で研修する場合は地域に密着した医療活動を通して福祉システムや地域包括ケアなどについて理解を深めます。日本海総合病院で再度研修を行う場合は、リエゾン・コンサルテーションや緩和ケアを中心に経験を積みます。山形大学医学部附属病院での研修を継続する場合は学術活動を継続し、学位取得に繋げることも可能です。精和病院で研修する場合は、通院患者リハビリテーション事業、地域移行、地域定着支援事業など地域精神保健福祉活動、地域との医療連携についても学ぶことが可能です。何れの施設においても指導医のスーパーバイズを受けながら単独で入院患者の主治医となり、責任を持った医療を遂行する能力を身につけます。
![]()
《山形県立こころの医療センター》山形県鶴岡市
 従来より民間病院では対応困難とされた症例を県内中から積極的に引き受けてきた伝統がありますが、現病院ではそれに加えて、民間の精神科病院では採算上の問題やマンパワーの問題から、なかなか着手できない政策医療の領域、すなわち精神科救急医療、児童思春期精神科医療、司法精神科医療(医療観察法)などの分野にも専門性の高い病棟を設立し、対応しています。
従来より民間病院では対応困難とされた症例を県内中から積極的に引き受けてきた伝統がありますが、現病院ではそれに加えて、民間の精神科病院では採算上の問題やマンパワーの問題から、なかなか着手できない政策医療の領域、すなわち精神科救急医療、児童思春期精神科医療、司法精神科医療(医療観察法)などの分野にも専門性の高い病棟を設立し、対応しています。
○精神科救急病棟
急性期で症状の激しい症例を24時間365日受け入れています。
即ち幻覚妄想により暴力などの問題行為や支離滅裂な言動を呈しているケース、躁状態で攻撃性や興奮が著しく周囲の手に負えなくなったケース、うつ状態で自殺企図に及んだケース、認知症の周辺症状による問題行動に至ったケースなどに対応しています。
看護師、精神保健福祉士、公認心理師などの多職種で関わり、急性期クリニカルパスを効果的に運用することで、短期間での退院を目指す集中的な治療を行っています。
○児童思春期病棟
15歳以下の患者を対象としており、院内学級(山形県立鶴岡養護学校おひさま分教室)を併設しています。
教師や公認心理師、看護師、作業療法士と連携しながら、発達障害児の行動異常、被虐待児の精神症状、摂食障害などに対して個別カウンセリング、集団療法、原籍校との環境調整など治療を行っています。
○重症慢性期病棟
統合失調症や双極性障害の治療困難例が主で、更なる治療と退院を目指し治療を行っています。また、治療困難例が多い本病棟ではクロザピンによる治療例も豊富です。
○ストレスケア病棟
うつ病や不安障害、適応障害などの患者が主に入院しています。
個室を増やしアメニティを重視した構造。薬物療法の他、疾病心理教育、認知行動療法などのプログラムによる治療を学ぶことができます。
○社会復帰病棟
救急病棟や重症慢性期病棟で治療を受け、病状がある程度改善した患者が主な対象です。
社会復帰のためのリハビリテーションプログラムが充実しています。
○医療観察法病棟
精神障害が基となって殺人、放火、強盗、強制性交など重大犯罪に至った事例が入院し、多職種で構成されたチーム、更に社会復帰調整官を初めとした院外の関係機関と連携した治療を行います。医療観察法病棟としては東北以北で2番目の開設となります。
○その他
・修正型電気けいれん療法を学ぶことができます。麻酔科医の応援を得て、全身麻酔下で年間200件以上施行しています。
・県の児童相談所に協力し、乳幼児の発達障害精密検査事業に従事しています。また、各種講演会講師、保健所、児童相談所、市や県の事業(自殺予防ネットワーク、うつ病診療連携など)、老人・知的障害者の施設、企業の産業医活動、看護学校の講師など地域における精神科のニーズにも積極的に応えています。
・デイケアや作業療法など慢性期患者の精神科リハビリテーションが充実しています。
精神障害者のスポーツによる社会参加を支援し、特に日本スポーツ精神医学会や日本ソーシャルフットボール協会とも協働したフットサルの取り組みは全国的にも注目されています。
・訪問看護や地域の作業所、グループホームとの連携など退院後の社会復帰について力を入れています。
・医局内では、ケースカンファレンス、脳波判読会、文献抄読会などを定期的に開催しています。
・慶應義塾大学先端生命科学研究所、ヒューマンメタボロームテクノロジーにおけるうつ病バイオマーカーの研究開発に協力した実績があります。
・全国規模の学会や研修会への参加を奨励し、発表や論文作成の際は指導を行っています。
《山形大学医学部附属病院精神科》山形県山形市
 ・身体合併症を有する措置入院患者を積極的に引き受けており、また、うつ病や統合失調症の医療保護入院の症例は豊富にあります。
・身体合併症を有する措置入院患者を積極的に引き受けており、また、うつ病や統合失調症の医療保護入院の症例は豊富にあります。
・総合病院の強みを活かして修正型電気けいれん療法も行っています。
・摂食障害や発達障害などの児童青年期患者の入院加療も数多く行っています。
・毎週開かれる症例検討会や論文抄読会、精神薬理・薬理遺伝学の勉強会、画像診断学・認知症の勉強会、発達障害・児童思春期の勉強会を開催しており、薬物療法、画像認知機能検査、画像診断、心理検査、精神療法など幅広い手技や治療法に習熟できます。
・臨床精神薬理学、薬理遺伝学、老年期精神医学などの最先端の研究に触れ、論文抄読や学会発表指導を受け、精神科医として必要なリサーチマインドを涵養させることができます。
・臨床面においても、難治性うつ病や摂食障害など大学病院ならではの症例を学ぶことができます。
《地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院》山形県酒田市
 ・三次救急にも対応した救命救急センター設置した総合病院です。
・三次救急にも対応した救命救急センター設置した総合病院です。
救命救急センターには自殺企図を初めとした精神科的問題を有する患者が数多く受診し、精神科と当該診療科が密接に連携して治療にあたっています。
・総合病院として、緩和ケアやリエゾンコンサルテーションなど、精神科医の治療介入について学ぶことができます。
・認知症疾患センターも設置され、MRI、SPECT、脳波、神経心理学的検査などによる精度の高い診断を学ぶことができます。
・修正型電気けいれん療法を学ぶことができます。日本総合病院精神医学会ECT研修施設に認定されており、年間約10例(約100回)実施しています。
・他科の医師と同様に全科救急当直を担当し、精神科のみならず全人的な医療を初期研修から継続して身に付けることができます。
《医療法人 東北会 東北会病院》宮城県仙台市
 ・仙台市中心部に位置する都市型の単科精神科病院です。創立117年を迎え、統合失調症、アルコール依存症を始めとする物質使用障害、気分障害、神経症性障害、摂食障害、パーソナリティ障害と対象疾患は多岐に渡ります。
・仙台市中心部に位置する都市型の単科精神科病院です。創立117年を迎え、統合失調症、アルコール依存症を始めとする物質使用障害、気分障害、神経症性障害、摂食障害、パーソナリティ障害と対象疾患は多岐に渡ります。
・入院に関しては物質使用障害・嗜癖性障害の専門病棟を持ち、アルコール・薬物リハビリテーションプログラムを基盤とし、患者個々の状態に応じ、各種集団療法等を組み合わせた治療を行うことができます。
・気分障害や神経性障害患者の入院も受け入れており、統合失調症は初発例、急性期、慢性期と多彩です。
・医療保護入院などの非自発的入院や行動制限を必要とする患者にも対応しています。
・治療としては、各種集団精神療法(アルコール、薬物、ギャンブル障害、摂食障害、女性アディクション患者、家族対象)が充実しており、集団力動を活用した支援に力を入れています。
・心理教育プログラムとして物質使用障害やギャンブル障害のワークショップを定期的に開催しています。
・地域連携としては、医師やコメディカルスタッフが仙台市のみならず宮城県全域の行政機関でスーパーバイズを行うほか、「宮城県アディクション問題研究会」では事例検討や講義等の話題提供を通して医療を超えた領域(行政、教育、司法、福祉)との連携を図っています。
・回復支援施設との連携、相互支援(自助)グループ設立支援など三次予防にも力を入れています。
《医療法人社団 愛陽会 三川病院》山形県三川町
 ・認知症病棟(48床)、精神療養病棟(48床)、医療療養病棟(内科系)(98床)の計194床にて診療を行っています。
・認知症病棟(48床)、精神療養病棟(48床)、医療療養病棟(内科系)(98床)の計194床にて診療を行っています。
・認知症病棟や医療療養病棟(内科系)などにおいて、認知症の周辺症状への対応、介護施設との連携、身体合併症の管理、退院支援などの地域包括的な精神科医療を学ぶことができます。
・精神系病棟の入院患者の症例は広く精神障害全般に亘り、措置入院も少数ではあるが受け入れています。
・認知症病棟は認知症系疾患全般の患者さんを受け入れています。BPSDへの対応、症状進行の可能な範囲の予防、生活機能訓練、専門的薬物療法の治療を経験できます。
・障害者総合支援法による福祉施設と、介護保険による有料老人ホームの運営も行っているため退院後の継続的総合的支援の実践経験も積むことができます。
・認知症初期集中支援チーム、知的障害者更生施設や特別養護老人ホーム、障害者総合支援法によるグループホーム、就労支援施設、学校医や精神保健相談業務の体験も可能なプログラムとなっています。
《沖縄県立精和病院》沖縄県南風原町
 ・沖縄県の県立精神科単科病院です。一般精神科医療に加え、民間病院では対応困難な患者さんの治療の担い手として、また、特に精神科救急については、沖縄県内においてその中核病院としての役割を果たしています。
・沖縄県の県立精神科単科病院です。一般精神科医療に加え、民間病院では対応困難な患者さんの治療の担い手として、また、特に精神科救急については、沖縄県内においてその中核病院としての役割を果たしています。
・許可病床数250床のうち、結核予防法に基づく結核指定病院としての病床が4床、応急入院指定病院としての病床が1床となっており、保健・福祉行政や他の医療機関、福祉施設との連携を行いながら、医療観察法の指定通院期間として、さらには、各種の教育・臨床研修を行う施設としての役割を担っています。
・指導医6名(常勤医10名)の充実した指導体制と、確立された専門治療環境のもと、精神科救急を含め、急性期から慢性期の主要な精神科症例を網羅する豊富な症例を経験できます。
・通院患者リハビリテーション事業、地域移行、地域定着支援事業など、地域精神保健福祉活動を推進しており、地域との医療連携についても学ぶことができます。
・諸島県ならではの離島診療所と連携した精神科巡回診療を経験できます。
・「ユタ」などのシャーマニズムによる伝統的民間療法と現代精神科医療の共存を通して比較文化精神医学を学ぶことができます。
《東京医科大学病院》東京都新宿区
 ・都心に位置する特定機能病院として、良質で高度な医療を提供しています。
・都心に位置する特定機能病院として、良質で高度な医療を提供しています。
・標準治療はもとより、新規医療技術の開発や種々の臨床研究を積極的に行っています。
・メンタルヘルス科の診療はメンタルヘルス科病棟、メンタルヘルス科外来、コンサルテーション・リエゾンサービスの3つの柱に分かれています。
・19床の閉鎖病棟に約10人/月の新入院患者を受け入れ、薬物療法、精神療法、環境調整を治療の主体としていますが、治療抵抗例には修正電気けいれん療法を行っています。
・外来では3,600人/月の診療にあたっており、多彩なケースを診ることができます。
・総合病院のメンタルヘルス科として、約60人/月の患者に対しコンサルテーション・リエゾンサービス(CLS)を行っています。
![]()
基本的には研修基幹施設である山形県立こころの医療センターの就業規則(山形県病院事業局就業規程)に
基づき、勤務時間、休日等を規定します。
- 勤務時間… 8:30~17:15(休憩時間60分)
- 当直勤務…17:15~翌8:30
- 給 与…山形県病院事業局職員の給与の支給に関する規程に基づき支給されます。
※詳細はお問い合わせください。 - 休 日…土曜日、日曜日、国民の休日、その他山形県病院事業局就業規程に規定する休日
- 年次有給休暇…山形県病院事業局就業規程に基づき付与します。
- そ の 他…夏季休暇、産前産後休暇、忌引休暇等山形県病院事業局就業規程に規定する休暇を
請求に応じ付与します。 - 学 会 等…本プログラム実施中の専攻医には、日本精神神経学会総会、同地方会、日本精神科
医学会等への出席の旅費は研修施設で負担します。
※医師(専攻医)は当専門プログラムへの採用後、研修施設群のいずれかの施設の職員となり研修を行います。
当院職員となり研修を行う場合は上記の勤務条件となります。
また、研修連携施設の職員となり研修を行う場合には、当該研修連携施設の就業規則等に則り勤務することになります。
![]()
ご質問や詳細は、下記までお問い合わせください。
山形県立こころの医療センター 総務経営課
0235-64-8100
0235-24-1283
ycocoro@pref.yamagata.jp